外壁塗装情報 |
神奈川区で幕板と雨樋上塗りで耐久性アップ |
| 人気blogランキングへ |
|
今回は過去に施工した事例から、神奈川区白幡向町で1月27日に行った幕板、雨樋の上塗り作業風景をお送りします。
幕板、雨樋は1月17日に中塗りを終えているので、この日は上塗りをして塗替えを完了させます。
中塗りまでにつけた塗膜に、より厚みと光沢を付加して耐久が高く、美しい塗装に仕上げていきます。
 幕板は上下端から塗布し、そのあと中央の広い面を塗ります。仕上げた外壁に塗料を付着させないように、細部から塗り始めるのです(専門用語でダメ込みとも)。段々になっているところは幅に合わせて刷毛を替え、細かな部分にもしっかり塗料を付着させています。塗布し終えた面はツヤツヤと光沢が出ているのが見えるでしょうか。
 こちらは雨樋の上塗りです。飛散の少ないローラーを使用して仕上げ塗装をしています。刷毛塗りでは刷毛目が出やすくなってしまいますが、このローラーは平滑に仕上がるタイプで、塗料の含みもよいので液ダレが起こりにくいのです。雨樋がピカピカになるように塗料をよく重ねて厚みのある塗膜をつけて仕上げました。
幕板、雨樋が仕上がったことで、こちらの現場での施工も残りわずかとなりました。次回は屋根の縁切りをして、タスペーサーを入れる工程に入ります。
|
神奈川区で雨戸塗装、外して塗ります。 |
| 人気blogランキングへ |
|
今回は過去に行った神奈川区での施工から、1月25日の雨戸塗装の作業風景をお送りします。職人は一級塗装技能士の川口が担当。
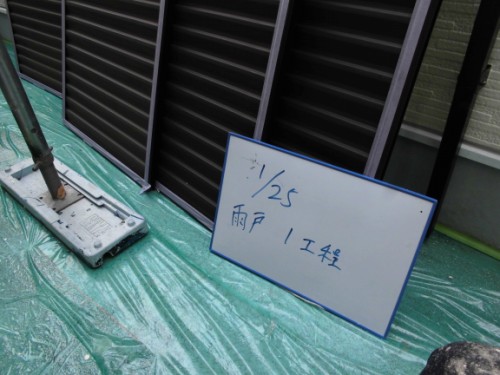 雨戸は塗りやすいように、設置してある場所から外して立てかけています。雨戸の四隅にはマスキングテープで養生をしました。塗装面は鉄部ですが、周囲はスチール製で塗替えをしないため、塗料が付着しないように覆う必要があるのです。この養生で塗り分け線が出るので、テープを真っ直ぐに貼り、途中で剥がれてこないように手でよく押さえておきます。雨戸の養生に関しては、下地調整を終えてから行う場合も。
 養生後は下地調整をします。鉄部は下地がツルツルとしてるため、そのまま塗料を重ねても剥がれやすくなってしまいます。そのため、ハンドパットやサンドペーパー(紙やすり)といったケレン道具で表面を研磨して、ごく微細な傷をつけることで塗料の食い付きを向上させます。せっかく仕上げた塗装があまり長持ちせず、すぐに剥がれてきては困りますよね。塗装工事では、塗料を重ねてからではわからない(見えない)工程が塗装の耐久性を左右させるのです。
 入念に下地調整をしたあとは、プライマーを塗布してさらに塗料がしっかり密着するように下塗りします。
サビが発生している場合はここでサビ止めを使用して、再びサビが発生することを抑制させます。サビ止めの色は何種類もありますが、仕上がりの色に合わせて選択。その中でもよく使用されるのは、赤錆び、茶、白、グレーなどです。
刷毛で一段ずつたっぷりプライマーを塗り終えたら、次は中塗りです。雨戸の端は塗りにくいため、刷毛でつつくようにして奥まで塗料を塗り込みます。厚みのある塗膜に仕上がるように段ごとにたっぷり塗料を重ねていきました。
 最後は上塗りをして3度塗りの仕上げです。今回は塗料の飛散が少ないローラーを使用して上塗りをしました。通常のものですと、雨戸のような凹凸がある場合にはあちらこちらに塗料が飛散してしまうのですが、このローラーは塗料の含みがよく、平滑に仕上がる上に飛散が少ないという多機能なものです。
中塗り時点でもツヤは出ていますが、さらに塗料を重ねるときれいな光沢が輝きます。外壁や屋根が塗替えによって美しく蘇るので、雨戸といった付帯部分も同様に仕上げていきました。
雨戸や戸袋塗装では、刷毛やローラーのほかにスプレーでの吹き付け塗装を行うこともあります。吹きつけ塗装では刷毛目が出ることがないですし、スピーディーに仕上がるという利点があるのです。ただ、塗料の飛散があるので(養生は徹底しています)、お宅の広さがあり、周囲に住宅がないなどの作業環境が求められます。
これで雨戸塗装が完了したので、次回は幕板や雨樋の上塗りに入ります。
|
神奈川区で付帯の塗装と屋根中塗り1回目 |
| 人気blogランキングへ |
|
神奈川区白幡向町で1月17日に行った過去の施工風景をお送りします。今回は付帯部の下・中塗りと屋根の中塗り1回目を行いました。
 まずは雨樋の下塗りです。下地と塗料の密着度を強化して、塗膜を剥がれにくくするために接着剤の役割を果たすプライマーを塗布します。透明な材料なので塗り落しがないように、見る角度を変えながら雨樋全体にムラなく塗り込みました。
 こちらは破風の下塗りです。同様に塗料の食い付きがよくなるように下塗りしていきます。
 続いて鉄部の中塗りをしています。下塗りでは白いサビ止めを塗布し、中塗りでは少しクリームがかった色を塗布しています。刷毛のストロークは大きく上下に動かして、刷毛目が出ないように仕上げていきます。たっぷり塗料を重ねて厚膜を形成しながら、艶やかな塗装面に。
 先ほど行った雨樋と破風の下塗りを充分に乾燥させたあとは中塗りに入ります。中塗り主材を刷毛でたっぷり塗布して塗膜をつけていきました。
破風は横樋がかぶさっている部分もありますが、わずかにある隙間に刷毛を差し込んで塗料を塗布していきます。場合によっては、下から覗くだけではなく上から覗き込むようにして、全体に塗料が行き渡っているか確認しつつ仕上げます。
塗装する場所によって、適した道具に持ち替えて隅々までムラなくきれいに塗膜をつけていきました。
  雨樋の集水器部分は凹凸があるので、窪みに塗料がたまらないように均一に仕上げていきます。幕板(帯板)は壁との境界を刷毛で線出しし、細部を仕上げてから全体に塗り広げます。
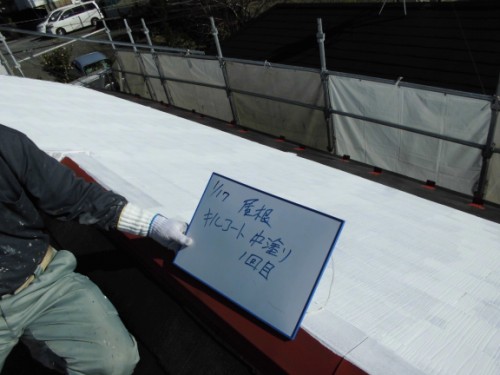  次は場所を変えまして、屋根の中塗りです。今回は断熱塗料のキルコートを使用。この材料は太陽熱を反射する遮熱と断熱効果があり、この二つの性能で屋根下の室温の上昇を抑制します。真夏にはサウナのような部屋になってしまう2階の部屋も、1階と同じくらいの室温になるので冷房器具の使用量も削減する効果が期待できます。
キルコート主材には熱の通過を抑制する中空ビーズというものがたっぷり含まれています。中空ビーズは比重がとても軽く、塗料を開封したら上層に浮いている状態のため、撹拌機でしっかり混合してから使用します。
屋根の細部はあらかじめ刷毛で塗り込んでから、ローラーで全面に塗装しました。この主材、見た感じではぼってりと重たそうに感じますが、中空ビーズが含まれているためかとても塗り心地が軽いと職人からも評判です。
キルコートは下塗り1回、中塗り2回、上塗り2回の計5回で仕上げるため、とても厚みのある耐久性の高い塗膜に仕上がります。また、この塗料は屋根のみならず外壁にも使用できるので、家丸ごと塗装をすることで、より断・遮熱性能が発揮されます。
|
お見積もり・お問い合わせフォーム









































